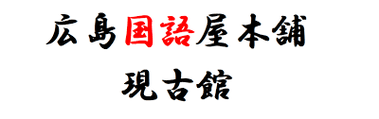広島国語屋本舗 現古館、館長の小林です。
国公立の二次試験を直前に控え、広島県公立高校入試の対策もいよいよ大詰め、といった状況です。
例年似たようなことしか書いていないのですが、2週間くらい前の朝日新聞に掲載された私の記事をコピペしておきます。
そうです、手抜き投稿です。
複数の資料を読み解く訓練を
令和5年度広島県公立高校入試・国語は、例年独立した大問として出題されていた200字から250字程度の小作文が大問3に吸収され、大問3つの形式で出題された。
新たな傾向として、大問2で複数の文章が提示されたり、事実と意見を区別する問題が出題されたりしたが、全体として見ると記述字数は160字ほど減少し、時間的制約は緩和されたと見てよい。
平均点は令和4年度から1.6点上昇した26.2点であった。
ただし、平均点が上昇したからと言って、易化傾向にあると安易に判断してはいけない。
部分正答はある程度許容されてはいるものの、正答率が20%を下回る問題は25点分、全体の実に5割にのぼる。
問題文や資料の中に解答を導くための巧みな誘導があるのは変わりないが、それに気付くためには、やはり適切な対策が必要だ。
よって、ここでは〈複数の資料に効率よく目を通す方法〉に焦点を絞って紹介したい。
全ての資料は、本文との関連の中で提示されるものであるから、まずは本文の内容理解を優先しよう。
登場人物の複雑な心情について問われる大問1であっても、【生徒の会話】という形で、内容理解のためのヒントが与えられる。
難解な表現1つ1つに時間をとられず、ヒントの登場を信じて先に進むことも重要である。
次に、問題文を丁寧に読み取り、問われている内容を精確に把握してほしい。
そうすることで、資料の中からどういった情報を取り出せばよいのかが定まる。
注意しておきたいのは、複数の文章の共通点を捉える問題だ。
Aの文章の内容と共通する表現がBの文章にあったとして、問われ方によってはただ書き抜くだけでは解答にならない場合がある。
Bの文章の内容を、Aの文章を踏まえて部分的に書き換えなくてはならないこともあるので、設問条件を可視化する習慣もつけておきたい。
問題文や資料に線を引いたり丸をしたりするなどして、「ただ読む」という作業から卒業しよう。
以上のことを踏まえて、入試本番まで3週間となった今、受験生の皆さんにできること。
それは広島県公立高校入試で過去に出題された問題を、実際に50分を計って解いてみることだ。
ただ解くのではなく、どのように解くのかを意識して解くこと。
この訓練を積んでいけば、皆さんの学力は飛躍的に向上するはずだ。
「問いに答える」「ヒントがある」。
この2点を念頭に置いて、悠然と本番に臨もう。